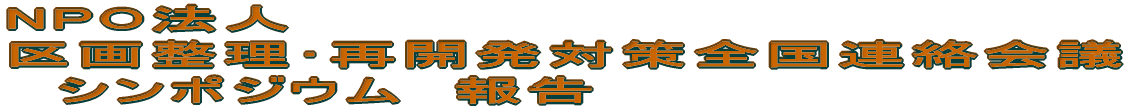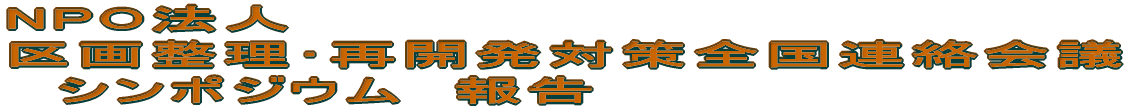■「区画・再開発通信」
2011年9月号から
■トップページへ
■シンポプログラムへ
「法改正」区画整理における住民の知る権利
―住民発意で「法改正」を考える・第2弾―
「区画・再開発通信」編集部・田村祐亮
●法改正をあえて議論する場
八月二二日、専修大学にて「シンポジウム 区画整理における住民の知る権利―住民発意で「法改正」を考える・第二弾―」が開催された。主催は熊さん八ッつぁん法律問題研究会、専修大学法学部行政法研究室(白藤博行教授)、NPO法人区画整理対策全国連絡会議の三者である。
まず、岩見良太郎氏(連絡会議代表世話人、埼玉大学経済学部名誉教授)のあいさつと主旨の説明がなされ、シンポジウムは幕を開けた。
●都市計画決定以前の住民参加へ
今回も前回に引き続いて住民発意での「法改正」を掲げているが、総花的なものではなく、「区画整理」さらには「住民の知る権利」に焦点を絞った議論が交わされた。
はじめに栗阪伸生氏(社団法人街づくり区画整理協会)から「土地区画整理事業における情報公開のガイドライン(案)」の活用について提起があった。栗阪氏はガイドラインを事業施行者と地権者の情報共有を図るためのツールであるとし、ガイドラインを活用して民主的な事業運営を図ってほしいと発言した。
また、土地区画整理法は、仮換地指定の前に換地計画を作成することを想定した構成になっている。そのように運用をすることで、換地計画について「公衆の縦覧」「意見書の提出」「法八十四条の備付簿書の閲覧」という制度の趣旨がはじめて活かされる、と述べた。
●情報公開について、現場から
次に三名から各地の事例報告が行われた。埼玉県桶川市の北村文子氏からは、組合区画整理事業の会計帳票類の開示について報告された。二年近くにわたり、組合帳簿を追い続けた北村氏らは、使途不明金や不可解な預金の流ればかりでなく、業者との癒着を疑わざるを得ない契約工事まで明らかにしつつあるという。
第二十八条九項を活用した帳簿及び書類の閲覧・謄写は、組合区画整理の破たん処理問題について大きな指針を与えそうだ。
東京都江戸川区の堀達雄氏(連絡会議代表世話人)からは「スーパー堤防・区画整理」事業にまつわる報告が成された。堀氏は都市計画決定以前に二割を超える地権者が地区を去ったことに言及し、「情報公開」以前の「情報操作」によって住民に亀裂が入ってしまったことを告発した。
東京都羽村市の神屋敷和子氏(羽村駅西口区画整理反対の会)も、堀氏の声を引き取る形で、住民による検証と合意がないままに行われる都市計画決定を激しく批判した。また、住民間での公平性を担保するためにも、仮換地指定前に換地計画の縦覧を行うべきであると述べ、先の栗阪氏の発言どおり、土地区画整理法の原則に立ち返ることを主張した。
●ガイドライン活用と法改正
これらの報告を受け、連絡会議事務局長の遠藤哲人氏は、習志野市の強制執行なども事例に挙げ、これまでの区画整理行政改善の流れに対する逆流が見られると発言した。すなわち「権力行政としての区画整理」が復権し、時間管理の概念とともにその暴力性をむき出しにしているとの指摘である。
土地区画整理事業が真に市民社会に馴染むツールたりうるには、先ずは、「情報公開ガイドライン(案)」の活用はもとより、都市計画法改正による「都市計画決定以前の情報公開、説明・住民の意見聴取手続きの義務づけ」、土地区画整理法改正による「仮換地段階での情報開示規定」が必要との見解を述べた。
以上の報告を受け、コメンテータとして岩見氏は、「縦の情報公開」(行政―住民)と「横の情報公開」(住民相互)の二つの座標軸を提起、コメントした。都市計画や事業計画の縦の情報公開は行政対住民の力関係で決まるが、換地関係の情報公開は複雑な図式となる。すなわち、法的には「縦の情報公開」として求められるが、それは実質的には「横の情報公開」であり、したがってその実現にとっては、住民間の信頼関係、結束が決定的に重要になると指摘した。
●情報公開の前提とは、活用とは?
報告者の報告を受け、最後に会場全体での討論が行われた。
討論では権利者としても住民としても「まちづくり」を進める上での横の情報はあくまでも全員に共有されるべきとの意見が大勢を占めたが、他人の情報を知る権利の根拠をどこに求めるのか。知られたくない権利もあるのではないか。という声も出た。
これに対し、「情報公開」や「知る権利」は元々のコミュニティの成熟や信頼関係の上に議論されるべきものだという意見や、施行者や行政との関係において「どのように情報公開がなされ、なされなかったのか」の検証が住民運動には重要であるとの討議も加えられた。
今回は区画整理における「知る権利」がテーマとなったが、事業の構想段階でいかに住民の意思を盛り込むのか、公開された情報や得た情報をどのように活用するのかなど、区画整理事業のみならず、普遍性ある問題提起と議論がシンポジウムの場で深められた。
(まとめ・田村祐亮)